歯周病が血糖値に影響するって本当?糖尿病との深い関係とは?
こんにちは。スマイルパートナーズ山手歯科クリニックです。
糖尿病と歯周病は、一見関係がなさそうに思えるかもしれませんが、実はお互いに影響を与え合う“相互関係”がある ことが、近年の研究で明らかになっています。糖尿病があると 歯周病にかかりやすくなり、一方で、進行した歯周病は 血糖コントロールを悪化させる という悪循環が起こることも。
でもご安心ください。適切なケアを行えば、この悪循環を断ち切り、お口の健康も血糖値も安定させることが可能です。
今回は、糖尿病と歯周病の関係や、予防・治療のために知っておきたいポイント解説していきます。大切な身体とお口の健康を守るために、今できるケアから始めてみませんか?
1.こんなお悩みありませんか?
 歯科の現場でも、糖尿病と歯周病に関するご相談は本当に多くなってきています。
歯科の現場でも、糖尿病と歯周病に関するご相談は本当に多くなってきています。
「最近歯茎が腫れていて、糖尿病もあるから心配で…」そんなお声をいただくこともよくあります。
- 「糖尿病と診断されたけど、歯周病にもなりやすいって本当?」
はい、これは多くの研究でも明らかになっている“お互いに影響しあう関係”なんです。 - 「歯茎が腫れたり、歯を磨くと出血するようになった」
このような症状、もしかしたら歯周病のサインかもしれません。特に糖尿病のある患者様は、炎症が悪化しやすい傾向があります。 - 「歯周病があると、糖尿病の数値も悪くなるって聞いたけど…?」
実はこれ、最近注目されている“口の健康と全身の健康のつながり”という考え方。お口の中の炎症が、血糖コントロールにまで影響することがあるんです。
糖尿病があるからといって、必ず歯周病になるわけではありません。
でも、糖尿病のある患者様は歯周病のリスクが高くなり、進行も早まることがあるため、「予防」や「早めのケア」がとても大切になります。
2.歯周病と糖尿病の関係とは?〜実はお口と血糖値は深くつながっています〜
 「歯周病は歯ぐきの病気、糖尿病は血糖値の病気。関係なんてあるの?」
「歯周病は歯ぐきの病気、糖尿病は血糖値の病気。関係なんてあるの?」
こんなふうに思われる方も多いと思います。ですが、近年の研究や医療現場での知見により、歯周病と糖尿病はお互いに影響し合うことがはっきりとわかってきています。
つまり、歯周病があると糖尿病が悪化しやすくなり、逆に糖尿病があると歯周病が進行しやすくなるという、いわば「悪循環」のような関係性があるのです。
歯周病が糖尿病を悪化させる理由
歯周病が進行すると、歯ぐきに炎症が起き、炎症性サイトカインという物質がたくさん作られます。
この物質は、血糖値を下げる働きを持つインスリンの作用を邪魔してしまうのです。結果として、血糖値が高くなりやすく、糖尿病のコントロールが難しくなってしまうのです。
たとえば…
- 歯ぐきの腫れや出血が慢性的に続いている
- 口の中がネバついたり、口臭が気になる
- 歯周病の治療をしていない状態が長く続いている
これらの状態があると、知らず知らずのうちに血糖コントロールに影響を与えている可能性があります。
糖尿病があると歯周病になりやすい理由
糖尿病のある患者様は、免疫力が低下しやすく、細菌に対する抵抗力も弱まっていることがあります。
また、高血糖状態では血管の働きが悪くなり、歯ぐきの毛細血管への栄養や酸素の供給が不十分になります。これが歯周病の進行を早めたり、治りにくくしたりする原因になります。
こんな症状に心当たりはありませんか?
- 歯ぐきが腫れたり、膿が出る
- 歯がグラグラする
- 歯みがきのときに毎回出血する
- 治療してもまたすぐに悪化してしまう
これらは、糖尿病による影響で歯周病が重症化しているサインかもしれません。
医学的にも証明されている「歯周病と糖尿病の深い関係」
近年の国内外の研究では、「歯周病の治療をしっかり行うと、血糖値(HbA1c)が改善される」というデータが多数報告されています。
つまり、歯周病のケアを行うことは、糖尿病の治療や予防にも役立つということです。
歯ぐきの健康を保つことが、全身の健康管理の第一歩になるという考え方が、今や医療の常識になりつつあります。
不安に思うことがあれば、ぜひ歯科でもご相談くださいね。お口の健康を整えることが、毎日の生活の質を高め、全身の健康を支える大きな力になります。
3.糖尿病の方が歯周病になりやすいのはなぜ?
 糖尿病と診断された患者様の中には、「最近、歯ぐきが腫れやすい」「歯みがきのときに出血しやすい」と感じている方が少なくありません。
糖尿病と診断された患者様の中には、「最近、歯ぐきが腫れやすい」「歯みがきのときに出血しやすい」と感じている方が少なくありません。
実は、糖尿病の状態が口の中にも影響を与えていて、歯周病のリスクを高めてしまうのです。
高血糖がもたらすお口の変化
糖尿病の特徴である「高血糖状態」は、血液中の糖分が常に高い状態です。
この状態が続くと、歯ぐきの毛細血管の働きが悪くなり、酸素や栄養が行き届きにくくなります。
結果として、歯ぐきが炎症を起こしやすくなり、歯周病が進行しやすくなるのです。
また、血糖値が高いと体の免疫機能も落ちてしまうため、炎症が治りにくくなったり、感染が広がりやすくなったりすることもあります。
免疫力が下がると、細菌と戦えない
糖尿病があると、体の免疫システムの働きが低下してしまいます。
そのため、本来なら退治できるはずの歯周病菌に対しても、抵抗力が弱くなってしまうのです。
✅歯ぐきが腫れやすい
✅膿が出やすい
✅歯を支える骨が徐々に溶けてしまう
といった症状が現れやすくなり、治療しても再発しやすい傾向があります。
唾液の分泌が減ると、さらに悪化しやすい
糖尿病の患者様によく見られるのが、「口の中が乾きやすい」という状態です。
これは、唾液の分泌量が減っていること(口腔乾燥症)が原因の一つ。
唾液には、口の中の細菌を洗い流す「自浄作用」がありますが、それがうまく働かなくなると、歯周病菌がどんどん繁殖しやすい環境に…。
唾液が減ることで起こるリスク
- 口臭が強くなる
- 歯ぐきの腫れや出血がひどくなる
- 歯周病の進行が早くなる
糖尿病のコントロールと同じくらい、お口の中の環境を整えることはとても大切です。
歯周病を予防・改善することで、血糖コントロールもしやすくなるという研究報告もあります。
4.歯周病が糖尿病を悪化させるのはなぜ?
 「歯周病と糖尿病、どちらかがあるともう片方も悪くなる」──そんな話を聞いたことがある患者様もいらっしゃると思います。実はこの2つの病気、お互いに深く関係していることが、最近の研究でも明らかになっています。
「歯周病と糖尿病、どちらかがあるともう片方も悪くなる」──そんな話を聞いたことがある患者様もいらっしゃると思います。実はこの2つの病気、お互いに深く関係していることが、最近の研究でも明らかになっています。
歯ぐきの炎症が、血糖コントロールを乱す
歯周病は、歯ぐきの中で「慢性的な炎症」が起こっている状態です。
この炎症が続くと、体内で“炎症性物質(サイトカイン)”が増えてしまいます。
この物質が血液にのって全身をめぐることで、インスリン(血糖値を下げるホルモン)の働きが弱まってしまうのです。
結果として…
- 血糖値がなかなか下がらない
- 食事や薬でコントロールしても効果が出にくい
- HbA1c(ヘモグロビンA1c)の値が高止まりしてしまう
つまり、歯ぐきの炎症があるだけで、血糖値に悪影響を与える可能性があるということです。
インスリンの働きが弱まる理由とは?
通常、私たちの体は、血糖値が上がるとインスリンを出してコントロールします。
でも、歯周病による炎症があると、そのインスリンの効きが悪くなる=「インスリン抵抗性」が高まる状態になります。
これは糖尿病にとって大きな問題で、
- 食後の血糖値が上がりやすくなる
- 糖尿病の合併症リスクが高くなる
- 薬の効果が出にくくなる
といった悪循環に陥りやすくなります。
歯周病を治療すると、血糖値が改善することも!
最近の研究では、歯周病をきちんと治療することで、血糖コントロールが改善されたという結果も報告されています。
歯ぐきの炎症が減ることで、体内の炎症物質も減少し、インスリンの働きが正常に戻りやすくなると考えられています。
✅歯周病治療のメリット
- 血糖値(特にHbA1c)が下がる可能性がある
- お薬の量や種類が変わることも
- 糖尿病の合併症リスクを減らすことにつながる
「糖尿病は内科だけで診てもらえばいい」
そう思いがちですが、実は歯科からのアプローチもとても大切なんです。
5.糖尿病がある方は特に注意!歯周病のセルフチェックと対策ポイント
 糖尿病をお持ちの患者様は、歯周病のリスクが高くなることが分かっています。
糖尿病をお持ちの患者様は、歯周病のリスクが高くなることが分かっています。
だからこそ、ご自身のお口の中に“いつもと違う変化”がないかをこまめにチェックすることがとても大切なんです。
こんな症状があれば要注意!歯周病セルフチェック
次のような症状に心当たりはありませんか?
- 歯みがきのとき、歯ぐきから出血することがある
- 歯ぐきが腫れている、または赤くなっている
- 歯がグラグラする感じがする
- 口の中がネバつく、乾燥しやすい
- 口臭が気になってきた
- 歯ぐきが下がって、歯が長くなったように見える
✅これらのサインは、歯周病の初期~中等度の症状であることが多いです。
「ちょっと気になるだけ」と思っても、放置せずに一度歯科でチェックを受けるのがおすすめです。
早期発見がカギ!歯科検診のすすめ
糖尿病があると、感染に対する抵抗力が落ちてしまうため、歯周病が進行しやすい傾向にあります。
そのため、通常よりもこまめな検診・メンテナンスが重要になります。
歯科検診でできること
- 歯ぐきの状態(出血・炎症)のチェック
- 歯の揺れや歯周ポケットの測定
- プラークや歯石の除去
- 自宅ケアのアドバイス など
✅とくに糖尿病の患者様は、3か月に1回のペースでの検診をおすすめしています。
歯周病の進行を防ぐためにできること
毎日のちょっとした習慣が、歯周病予防にはとても大切です。
次のようなことを意識してみましょう。
- 丁寧な歯みがき(1日2回以上、歯と歯ぐきの境目も意識)
- 歯間ブラシやデンタルフロスの併用
- バランスのよい食事と、糖質の摂りすぎを控える
- 十分な睡眠とストレスケア
- 定期的な歯科でのクリーニング
糖尿病と歯周病、両方を予防・改善していくには、お口と体の両方を大事にするケアがポイントです。
「まだ大丈夫」と思っている間に、症状が進んでしまうことも少なくありません。
気になるサインがある場合は、どうぞ遠慮なくご相談ください。
歯科は“歯を守る場所”であると同時に、“全身の健康を守る入口”でもありますよ。
6.糖尿病のある患者様にこそ大切な「歯周病予防の基本」
 糖尿病と歯周病は、互いに影響し合う関係にあります。
糖尿病と歯周病は、互いに影響し合う関係にあります。
そのため、糖尿病をお持ちの患者様は、日ごろからお口の健康にも特に気を配ることが大切です。
毎日のセルフケアが予防のカギ
正しい歯みがきと歯間ケアの習慣を身につけましょう
歯周病を予防するには、まずプラーク(歯垢)をきちんと取り除くことが基本です。
以下のポイントを意識してみてください:
- 歯ブラシは「毛先がしっかり当たっているか」を意識
- 歯と歯ぐきの境目を、やさしく小刻みに磨く
- 1回の歯みがきに3分以上かけるのが理想
- 歯間ブラシやデンタルフロスで、歯と歯の間の汚れも取り除く
✅ 糖尿病の患者様は免疫力が下がりやすいため、ほんの少しの汚れでも炎症につながることがあります。
毎日のケアを「丁寧に、やさしく、しっかりと」が合言葉です。
食生活でもお口の健康をサポート
お口と血糖値、どちらにもやさしい食習慣を意識しましょう
食事の内容や摂り方も、歯周病予防に影響します。
特に糖尿病をお持ちの患者様には、以下のような工夫がおすすめです:
- よく噛んで食べる(唾液がしっかり出て口腔内の自浄作用UP)
- 野菜や食物繊維をしっかり摂る(腸内環境と血糖コントロールをサポート)
- 甘い物や柔らかい食品に偏りすぎない
- 食後はできるだけ早く歯みがきをする
✅お口の健康は、体の内側からも守っていくことができます。
バランスのよい食事と丁寧な咀嚼(そしゃく)を心がけてみてください。
定期検診で歯ぐきを守る
「異常がないとき」こそ歯科を上手に使いましょう
歯周病は、初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。
だからこそ、定期的に歯科医院でチェックを受けることがとても大切です。
歯科検診でできること
- 歯ぐきの出血や腫れの有無をチェック
- 歯石の除去や、プラークの付着状態の確認
- 歯周ポケットの深さ測定(歯周病の進行具合を評価)
- 日々のケアに合わせたアドバイス
✅糖尿病をお持ちの患者様には、3か月に1回程度の定期検診をおすすめします。
「調子がいいから行かなくて大丈夫」と思わずに、ぜひ定期的に通っていただきたいです。
歯周病の予防は、「続けること」がいちばん大事です。
無理なく、毎日の習慣として取り入れていくことが、お口と体の健康を守る第一歩になります。
7.血糖コントロールと歯周病予防の関係 ~お口と全身の健康はつながっています~
 「歯周病は歯ぐきの病気」「糖尿病は血糖値の病気」と思われがちですが、実はこの2つはとても深く関係しています。
「歯周病は歯ぐきの病気」「糖尿病は血糖値の病気」と思われがちですが、実はこの2つはとても深く関係しています。
最近では、歯科と内科が連携して診療にあたることもあるほど、“口と体”のつながりが重要視されています。
とくに糖尿病をお持ちの患者様にとって、血糖コントロールは歯周病予防のカギとなります。
また反対に、歯周病が悪化すると血糖値のコントロールがうまくいかなくなるという“悪循環”も起きるのです。
なぜ血糖値が高いと歯周病になりやすいの?
糖尿病になると、体内の「インスリン」というホルモンの働きが悪くなり、血糖値が高い状態が続くようになります。
これによって免疫力が下がったり、体の炎症反応が強く出やすくなったりして、歯周病菌の影響を受けやすくなるのです。
高血糖が歯ぐきに与える影響:
- 歯ぐきの血流が悪くなり、酸素や栄養が届きにくくなる
- 傷の治りが遅くなり、炎症が長引きやすくなる
- 免疫細胞の働きが低下して、細菌に負けやすくなる
こうした状態が続くと、歯ぐきが腫れたり出血しやすくなり、歯周病がどんどん進行してしまいます。
歯周病があると血糖コントロールが難しくなる?
歯ぐきに炎症があると、そこから「炎症性物質(サイトカイン)」が出続けます。
この物質が血液を通じて全身に広がると、インスリンの働きを邪魔し、血糖値を下げにくくしてしまうのです。
つまり、歯周病があると、糖尿病の治療が難しくなることもあるということ。
だからこそ、歯科からのアプローチもとても大切なんです。
歯周病を治療すると、血糖値もよくなる?
近年の研究で、歯周病治療を行った糖尿病患者様の中には、ヘモグロビンA1cの数値が改善したというデータも出ています。
これは、歯周病を治すことで炎症物質の量が減り、体の中のバランスが整うためだと考えられています。
もちろんすべての方に当てはまるわけではありませんが、
「歯ぐきのケアも、糖尿病治療の一環」と考えていただくとよいかと思います。
生活習慣の改善が“お口と体”の健康を守るカギ
日々の生活を少しずつ見直していくことが、血糖値の安定にも歯ぐきの健康にもつながります。
こんな習慣を意識してみてください:
- 【運動】ウォーキングやストレッチなど、毎日少しでも体を動かす習慣を
- 【食事】食物繊維を多めに、よく噛んでゆっくり食べることで唾液分泌もアップ
- 【睡眠】十分な睡眠で体を整え、ストレスをため込まないように
- 【歯みがき】1日2回以上、丁寧なブラッシングと歯間ケアを続ける
- 【定期検診】糖尿病のある方は特に、3ヶ月に1回程度の歯科検診を
「歯ぐきが少し気になるけど、糖尿病とは関係ないかも…」と感じている方も、ぜひ一度歯科医院でチェックを受けてみてください。
8.歯周病治療を受ける際の注意点
 糖尿病があると、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、治療を受ける際にも少し注意が必要になります。
糖尿病があると、歯周病が進行しやすくなるだけでなく、治療を受ける際にも少し注意が必要になります。
ですが、しっかり準備をして臨めば、多くの患者様が問題なく治療を受けることができますのでご安心ください。
歯科と医科が連携して治療を進めることが大切です
糖尿病のコントロール状況(血糖値の安定度)によって、歯周病治療の進め方や注意点は変わってきます。
そのため、歯科だけでなく、糖尿病を診ている内科の主治医とも連携することがとても重要です。
✅たとえば…
- 血糖値が高くて感染リスクが心配な場合
- インスリンなどの薬のタイミングを考慮する必要がある場合
- 持病や薬の影響で、出血や治癒の回復に配慮が必要な場合
など、患者様の全身状態に合わせて、安全に治療できるように事前に連携をとるのが理想的です。
➡ 歯科医院を受診される際は、「糖尿病の診断を受けていること」や「内服中の薬の名前」などをきちんと伝えていただくとスムーズです。
麻酔や処置の際に気をつけたいポイント
歯周病治療では、歯ぐきの奥にある汚れを取るために麻酔を使ったり、場合によっては外科的な処置が必要になることもあります。
糖尿病がある場合、以下の点に気をつけることでより安全に治療を進めることができます。
麻酔や処置時の注意点:
- 食事や血糖測定のタイミングと治療時間を調整する
- 低血糖を防ぐために、空腹のまま来院しない
- インスリンや血糖降下薬を使用中の場合は、事前に医師と確認しておく
- 感染リスクが高い場合は、抗生物質の処方を含めて対応する場合がある
糖尿病の状態によっては、「今日は治療を見合わせて様子を見ましょう」といった判断をすることもあります。
決して無理せず、患者様の体調を最優先にしながら治療を進めていくのが基本です。
治療後の回復をサポートするためにできること
糖尿病をお持ちの患者様は、傷の治りがやや遅くなる傾向があります。
そのため、治療後のセルフケアや体調管理がとても大切です。
✅治療後に気をつけたいポイント:
- 出されたお薬(抗生物質・痛み止めなど)は、指示通りにしっかり服用する
- 傷口に触れすぎないようにし、うがいは優しく行う
- 食事は刺激物を避け、栄養バランスの良いものをとる
- 睡眠をしっかり取り、体をしっかり休める
- 血糖値が高めにならないよう、食事・運動を無理なく調整する
また、治療後に痛みや腫れが強く出たり、出血が止まらないといった場合は、すぐに歯科医院に連絡してくださいね。
糖尿病があるからといって、歯周病治療を諦める必要はまったくありません。
大切なのは、「今の体の状態に合った治療を、無理なく受けること」。
お口の健康を守ることが、全身の健康を守る第一歩になります。
9.糖尿病の人でも受けられる歯周病治療とは?
 「糖尿病があると歯周病の治療は難しいのでは…」
「糖尿病があると歯周病の治療は難しいのでは…」
そんなご不安の声を、患者様からよくいただきます。
たしかに、糖尿病をお持ちの方はお口の中の免疫力が落ちやすく、治療中のリスクや治癒に時間がかかることもあります。でも、ご安心ください。
現在では、糖尿病をお持ちの患者様でも安心して受けられる歯周病治療がしっかり確立されています。
無理なく続けられる治療方法の選び方
糖尿病のある患者様にとっては、「治療が負担にならないこと」「体に優しい方法で進めること」がとても大切です。
お口の状態や全身の健康状態に合わせて、次のような治療法を組み合わせていきます。
✅主な治療法の一例:
- スケーリング(歯石除去)
歯ぐきの上や奥に付着した歯石を丁寧に取り除き、炎症の原因を減らします。 - ルートプレーニング
歯の根元の表面を滑らかにし、細菌の再付着を防ぎます。局所麻酔を使う場合もあります。 - 歯周ポケット洗浄
歯周病が進んだ部位は、薬剤や専用の器具でしっかり洗浄し、炎症をやわらげます。 - レーザー治療や抗菌剤の使用
炎症が強い部位には、出血を抑えながらやさしく処置できるレーザーや抗菌剤を使うこともあります。
➡ ポイントは、「一気に治す」のではなく、「無理なく継続できるペースで、少しずつ丁寧に治療していく」ことです。
炎症を抑えるための最新治療もあります
近年は、従来の歯周病治療に加えて、より体に優しく、かつ効果的な治療法が増えています。
たとえば:
- 光殺菌治療(PDT)
特定の光と薬剤を使い、歯周病菌だけを狙って殺菌できる方法です。抗生物質に頼らないので、体への負担が少なく済みます。 - バイオフィルム除去のための超音波機器
歯の表面にこびりついた細菌の膜(バイオフィルム)を、音波で優しく取り除きます。 - 再生療法(必要なケースのみ)
重度の歯周病では、失われた骨や組織を再生させる処置を行う場合もあります。
こうした治療はすべて、患者様の体調や糖尿病のコントロール状況をしっかり確認したうえで行います。
決して無理はさせず、「いまの状態でできること」を一緒に相談しながら進めていきます。
歯周病の進行を止めるには“メンテナンス”がカギです
歯周病は、治療をしたあとも放っておくと再発しやすい病気です。
とくに糖尿病があると、体の免疫が低下しやすいため、「治療後のメンテナンス」がとても大切になってきます。
✅メンテナンスで大事なこと:
- 3〜4ヶ月ごとの定期検診で歯ぐきの状態をチェック
- 専門的なクリーニング(PMTC)で歯垢・歯石を徹底除去
- おうちでのケア方法を定期的に見直してもらう
- 必要に応じて、内科の先生とも連携しながら進めていく
歯ぐきの状態や血糖値のコントロールが安定してくると、「歯ぐきの腫れが引いた」「出血が減った」「口臭が気にならなくなった」といった改善を感じる患者様も多いです。
糖尿病があるからといって、「もう歯周病は治せない」と思う必要はありません。
大切なのは、患者様ご自身のペースに合わせた無理のない治療を、医師と一緒に相談しながら続けていくこと。
「治療が不安」「何から始めればいいか分からない」という場合も、まずはカウンセリングだけでも大歓迎です。
10.よくある質問
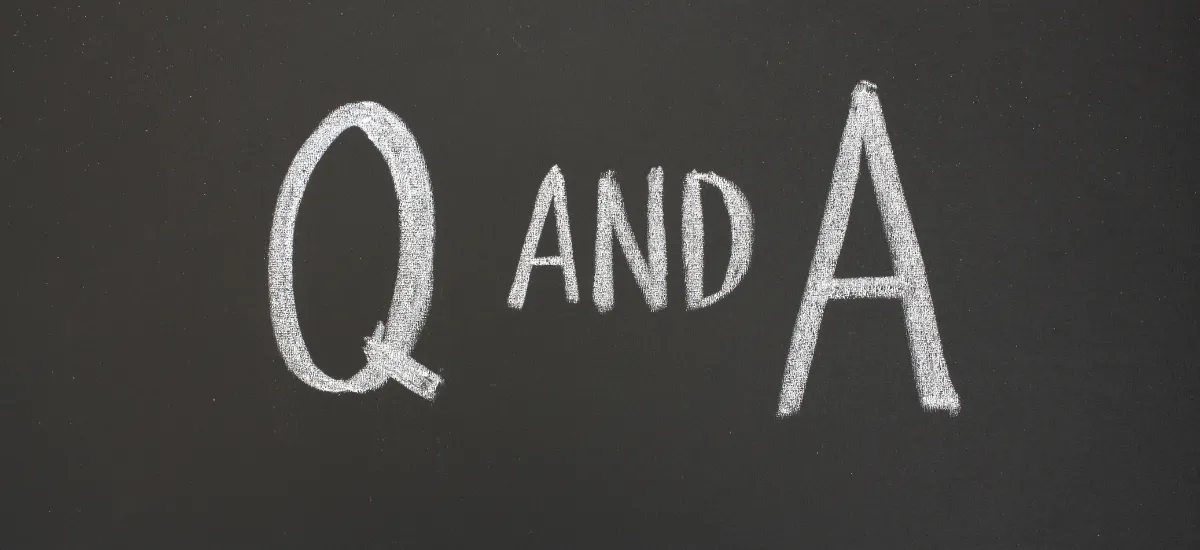 歯周病と糖尿病の関係についてご説明すると、多くの患者様からさまざまな質問をいただきます。
歯周病と糖尿病の関係についてご説明すると、多くの患者様からさまざまな質問をいただきます。
ここでは、特によく聞かれるご質問にお答えしながら、患者様の不安や疑問を少しでも軽くできるよう、お話ししていきますね。
Q1.「糖尿病があると歯周病は治りにくいって本当ですか?」
A1.はい、実はこれは本当です。糖尿病があると、体の免疫力が落ちたり、傷の治りが遅くなったりします。そのため、歯周病の炎症が治りにくくなることがあるんです。
ですが、悲観しすぎる必要はありません。
大切なのは、次の2つを並行して整えることです:
- 血糖値のコントロール(内科や自己管理で)
- 口腔ケアの徹底(歯科での治療や毎日のケア)
この2つをしっかり続けていけば、糖尿病があっても歯周病を改善することは十分可能です。
Q2.「血糖値が安定してくると、歯ぐきの状態も良くなりますか?」
A2.はい、これはとても良い質問です。
血糖値がコントロールできてくると、体の炎症反応も落ち着いてきます。
その結果、歯ぐきの腫れがひいたり、出血が減ったりする患者様も多くいらっしゃいます。
実際、歯周病治療と血糖コントロールを並行して進めたことで、
「HbA1c(ヘモグロビンA1c)の数値が下がった」
というデータも報告されています。
お口のケアは、実は糖尿病の治療の一部でもあるんですね。
Q3.「糖尿病でも歯周病を予防する方法はありますか?」
A3.もちろんあります! 予防は、治療以上に大事な部分です。
糖尿病のある患者様におすすめの予防法を、以下にまとめてみました。
✅今日からできる予防のポイント:
- 毎日の歯みがきを丁寧に
食後はもちろん、寝る前のケアを特にしっかり行いましょう。フロスや歯間ブラシも取り入れるとより効果的です。 - お口の中が乾燥しないように注意
糖尿病の影響で唾液が減りやすくなります。こまめな水分補給や、唾液腺マッサージがおすすめです。 - 甘いものの摂取は“控えめ”に
血糖値の管理のためにも、虫歯や歯周病予防のためにも、甘い飲み物・お菓子のとりすぎには注意しましょう。 - 定期的に歯科検診を受ける
歯ぐきの状態は、自分では気づきにくいものです。歯科医院でのチェックとクリーニングを習慣にしましょう。
Q4.歯周病の治療は痛いですか?
A4.ご安心ください。現在の歯周病治療は、できるだけ痛みを抑えた方法で進めることができます。
初期の段階であれば、歯石の除去やクリーニングが中心ですし、進行していても麻酔を使いながら丁寧に対応します。患者様の体調や糖尿病の状態にも配慮しながら治療しますので、不安なことがあれば何でもご相談ください。
Q5.糖尿病の薬を飲んでいますが、歯科治療に影響はありますか?
A5.はい、お薬の種類によっては治療内容に影響することもあります。
たとえば、血糖を下げる薬を服用されている方は、治療中に低血糖を起こすリスクがあるため、治療前に必ず医師と情報共有し、必要な調整を行います。歯科医院では、事前にしっかり確認しますので、服用中のお薬については遠慮なくお伝えくださいね。
歯周病と糖尿病。
一見まったく別の病気のように思えますが、実はお互いに深く関わっていて、どちらかを放っておくともう一方にも悪影響を及ぼしてしまいます。
- 糖尿病があると歯周病にかかりやすくなる
- 歯周病があると、血糖コントロールがうまくいきにくくなる
この「悪循環」を断ち切るには、お口と全身の健康を同時にケアすることがとても大切です。
大切なのは、“今できること”から少しずつ始めていくことです。
歯ぐきの状態が良くなると、お食事もしっかり楽しめるようになります。
お口の健康が整うことで、毎日の暮らしにも自信や笑顔が増えていきます。
もし不安なことや、わからないことがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
東京都品川区YDC精密歯周病インプラント治療専門ガイド
監修:医療法人スマイルパートナーズ 理事長/齋藤和重
『山手歯科クリニック大井町』
住所:東京都品川区東大井5丁目25−1 カーサ大井町 1F
『山手歯科クリニック戸越公園』
住所:東京都品川区戸越5丁目10−18
*監修者
*経歴
1990年 鶴見大学歯学部卒業。1991年 インプラント専門医に勤務。1999年 山手歯科クリニック開業。
2001年 INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS卒業。
2010年 医療法人社団スマイルパートナーズ設立。
*所属
・ICOI国際インプラント学会 指導医
・ICOI国際インプラント学会 ローカルエリアディレクター
・ITI国際インプラント・歯科再生学会 公認 インプラントスペシャリスト
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本顎顔面インプラント学会 会員
・国際審美学会 会員
・日本歯科審美学会 会員
・日本アンチエイジング歯科学会 会員
・INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS(2001年)
・CID Club (Center of Implant Dentistry)所属
・国際歯周内科研究会 所属
・5-D JAPAN 所属
・デンタルコンセプト21 所属
・インディアナ大学歯学部 客員 講師
・南カルフォルニア大学(USC)客員研究員
・南カルフォルニア大学(USC)アンバサダー
・USC (南カルフォルニア大学)歯学部JP卒
・USC University of Southern California)センチュリー・クラブ
・プレミアム・メンバー
※詳しいプロフィールはこちらより

