インプラント治療後に噛みにくいと感じたら?違和感の原因と対処法は?
こんにちは。スマイルパートナーズ山手歯科クリニックです。
インプラントは、見た目や噛む力を回復できる優れた治療ですが、噛み合わせがきちんと整っていないと、せっかくのインプラントが十分に機能しなかったり、トラブルの原因になることもあります。
実は、噛み合わせの微妙なズレが顎関節や他の歯に負担をかけたり、インプラントの寿命を縮めてしまうこともあるのです。そのため、インプラント治療では「噛み合わせの調整」も非常に重要なステップとなります。
今回は、インプラントと噛み合わせの関係、違和感を感じたときの対処法、噛み合わせを整えるためのセルフケアや定期的な調整の重要性について、ご紹介していきます。
「快適に噛める」「長くインプラントを使える」状態を保つために、ぜひ参考にしてみてください。
1.こんなお悩みありませんか?
 インプラントの治療を受けたあと、こんなふうに感じたことはありませんか?
インプラントの治療を受けたあと、こんなふうに感じたことはありませんか?
- 「なんだか噛み合わせがズレてるような気がする…」
- 「ごはんを食べるときに違和感がある」
- 「痛みはないけど、しっくりこない感じがある」
- 「せっかくインプラントにしたのに、本当にこれでいいのかな?」
実は、こうした「噛み合わせの違和感」は、インプラント治療後のご相談の中でもとても多いものなんです。
治療そのものは順調でも、少しのズレがあると噛んだときに違和感が出たり、あごが疲れたりすることもあります。放っておくと、周りの歯や筋肉にも負担がかかってしまう可能性もあるんですね。
インプラントは、見た目だけでなく“しっかり噛めてこそ意味がある治療”です。
「ちょっと気になるかも…」という小さなサインでも、どうかそのままにせず、遠慮なく私たちにご相談ください。
2.インプラントと噛み合わせの関係
 インプラント治療を受けたあと、「これでしっかり噛めているのかな?」「違和感はないけど、このままで大丈夫?」といったご不安を感じる患者様は少なくありません。
インプラント治療を受けたあと、「これでしっかり噛めているのかな?」「違和感はないけど、このままで大丈夫?」といったご不安を感じる患者様は少なくありません。
実は、インプラントの成功には“噛み合わせ”が大きく関わっています。見た目がきれいに仕上がっても、噛み合わせがズレていると、思わぬトラブルを引き起こす可能性があるんです。
噛み合わせのバランスが崩れるとどうなる?
噛み合わせがうまくいっていない状態では、以下のような問題が起きやすくなります。
- 他の歯やあごの関節に負担がかかる
- インプラント部分に力が集中してしまい、ネジが緩んだり破損の原因に
- 肩こり・頭痛・顔のゆがみなど、体の不調につながることも
天然の歯には“歯根膜”というクッションのような組織がありますが、インプラントにはそれがありません。そのため、少しのズレでも衝撃がそのまま伝わってしまい、負担になりやすいんです。
適切な噛み合わせとは?
インプラント治療後に大切なのは、以下のようなポイントがしっかり保たれていることです。
- 左右どちらか一方に負担がかかりすぎていないか
- 食事中に痛みや違和感がないか
- しっかり噛めるけれど、インプラントに過剰な力がかかっていないか
- 自然な噛み心地があるか
私たちは、インプラントの角度・位置・高さを一人ひとりのお口に合わせて丁寧に調整しています。特にかみ合わせの細かなチェックと調整は、長くインプラントを使っていただくために欠かせない工程です。
噛み合わせのズレが原因で起こりうるトラブルとは?
- インプラントの周りが炎症を起こしてしまう(インプラント周囲炎)
- 被せ物(人工歯)が欠けたり、外れやすくなる
- 食事の際に違和感や痛みを感じる
- インプラントの寿命が短くなる可能性も
一見、小さな違和感でも、放置すると徐々に大きな問題に発展することがあります。だからこそ、「なんとなく噛みづらい気がする」「最近ちょっと気になる」…そんな些細なサインも、早めにご相談いただくことが大切なんです。
インプラントは見た目だけでなく、しっかり噛めること、そして長く快適に使えることが大切です。
3.インプラント治療後に噛み合わせが変わってくる理由とは?
 インプラント治療を終えて、「なんとなく噛み心地が変わった気がする」「以前とはちょっと違和感がある」そんなふうに感じる患者様もいらっしゃいます。
インプラント治療を終えて、「なんとなく噛み心地が変わった気がする」「以前とはちょっと違和感がある」そんなふうに感じる患者様もいらっしゃいます。
それは決して珍しいことではなく、いくつかの理由が重なって、噛み合わせに微妙な変化が生まれることがあるんです。
顎の骨や歯並びの変化による影響
インプラントは顎の骨にしっかりと埋め込む治療ですが、その周囲の骨は加齢や生活習慣によって、少しずつ変化していくことがあります。
- 歯を失った期間が長いと、骨が痩せていることもあります
- 顎の骨にかかる力のバランスが変わることで、噛み合わせの高さが微妙に変わることもあります
- 周囲の天然歯が動くことで、噛み合わせがズレてくるケースもあります
特に長期間歯を失ったままにしていた場合、インプラントを入れることによって噛む力のかかり方が変わり、他の歯にも影響が出てくることがあるんです。
日常生活での癖も噛み合わせに影響を与えます
普段の何気ない癖も、実は噛み合わせを少しずつ変えてしまう原因になります。
たとえば:
- 食いしばりや歯ぎしり:寝ている間や無意識のうちに強く噛みしめてしまう方は要注意。インプラントに過度な力が加わることで、噛み合わせのバランスが崩れてしまうことがあります。
- 頬杖をつく癖:片方の顎だけに力がかかりやすく、噛み合わせに左右差が出てしまうことも。
- いつも同じ側で噛む習慣:左右どちらかに偏った噛み方をしていると、あごの筋肉や骨格にもズレが生じ、噛み合わせに影響します。
こうした日常の癖に気づかないままだと、せっかく治療したインプラントにも負担がかかりやすくなってしまいます。
インプラントが周囲の歯に与える影響も見逃せません
インプラントは人工の歯ですが、まわりの天然歯と一緒に使っていくものです。そのため、インプラントを入れたことで、噛むときの力のかかり方が変わり、隣の歯が少しずつ動いたり、歯列全体に影響が出る場合もあります。
- 特に奥歯のインプラントは力を多く受けるため、その影響で前歯の噛み合わせにまで変化が出ることも。
- 反対に、インプラントをきっかけに全体の噛み合わせが整うケースもあります。
噛み合わせは「少しのズレ」がやがて「大きな違和感」になることもあります。「なんとなく噛みづらい」「違和感がある」…そんな小さなサインを見逃さず、ぜひ定期的なチェックを受けてください。
インプラントを長く快適に使っていただくためにも、治療後の経過観察と調整はとても大切なステップです。
4.噛み合わせの違和感をそのままにしていませんか?
 インプラント治療を受けたあと、よく患者様からこんなお声をいただきます。
インプラント治療を受けたあと、よく患者様からこんなお声をいただきます。
「なんとなく噛みにくい気がする」「いつの間にか片側ばかりで噛んでいる」「違和感があるけど、そのうち慣れるかなと思って」──。
こういった“ちょっとしたズレ”や感覚の違和感、ついそのままにしてしまいがちですよね。ですが実は、これらはインプラントやお口全体が発している大切なサインかもしれません。
放置してしまうと、インプラント自体に問題が起きるだけでなく、お口全体のバランスを崩し、さらに体全体の健康にも影響を及ぼすことがあるんです。
インプラント周囲炎のリスクが高まる
噛み合わせがうまく合っていないと、インプラントに本来かかるべきではない強い力が加わるようになります。
天然の歯には「歯根膜(しこんまく)」というクッションのような組織があるため、噛む力をうまく分散できますが、インプラントにはこのクッションがありません。
そのため、噛む力がダイレクトに骨に伝わりやすく、負担が蓄積しやすいのです。
この過剰な負担によって周囲の歯ぐきや骨に炎症が起きやすくなり、最終的には「インプラント周囲炎」という病気に進行することもあります。
✅インプラント周囲炎の進行イメージ:
- 初期:歯ぐきが腫れる、軽い出血がある
- 中期:骨が少しずつ溶け始め、違和感が強くなる
- 重度:インプラントがグラグラしてきて、最悪の場合は脱落する
こうした症状は初期段階では自覚しにくいことも多く、違和感が“予兆”として現れている可能性があります。
「ちょっと変だな」と感じたら、インプラントが“助けて”と言っている合図かもしれません。
顎関節症(がくかんせつしょう)になるリスクも
噛み合わせの不調は、歯やインプラントだけの問題ではありません。
実は、あごの関節や筋肉にもじわじわと負担をかけてしまうのです。
噛み合わせのズレが長く続くと、上下の歯の接触がアンバランスになり、それに伴ってあごの位置もズレていきます。
この状態が慢性化すると、「顎関節症」という症状につながる恐れがあります。
✅こんな症状がある方は注意:
- 口を開けると“カクッ”と音がする
- あごの付け根が痛む、だるい
- 開けにくい・閉じにくい感じがする
これらの症状が日常的に現れるようになると、食事や会話がしづらくなるだけでなく、あごの動き自体が制限され、生活の質が下がってしまうこともあるのです。
肩こり・頭痛・姿勢のズレなど、全身の不調にも影響が
噛み合わせがずれていると、お口の中だけでなく体のバランス全体に影響する可能性があります。
- 噛み合わせが乱れると、噛むときに使う筋肉に偏りが出てきます
- その筋肉のバランスが崩れると、首や肩に力が入りやすくなり、慢性的な肩こりや首こりに
- 頭痛や目の奥の違和感、背中のこわばりを引き起こすことも
- あごのズレが体全体のゆがみに発展し、姿勢が悪くなったり、疲れやすくなったり…
つまり、たった1本のインプラントの“噛み合わせの違和感”が、全身の不調を招く引き金になることもあるのです。
違和感をそのままにしておくのではなく、「あれ?」と感じたらすぐにご相談いただくことがとても大切です。
5.噛み合わせを整えるためにできること
 インプラント治療後に「なんとなく噛みにくい」「口がスムーズに動かない」と感じることはありませんか?
インプラント治療後に「なんとなく噛みにくい」「口がスムーズに動かない」と感じることはありませんか?
実は、噛み合わせの違和感はちょっとしたサインかもしれません。
簡単にできる!噛み合わせセルフチェック
まずは、今の噛み合わせの状態を自分で確認してみましょう。鏡の前で以下のようなチェックをしてみてください。
✅口を閉じたときに、上下の前歯がぴったり合っていますか?
✅奥歯で「ギュッ」と噛んだとき、左右どちらかに強く当たる感じはありませんか?
✅噛んだときにカチカチ音がしたり、違和感を覚えることはありませんか?
✅食べ物を噛むとき、左右どちらかに偏っていませんか?
✅口を大きく開けるとあごがカクカク鳴る、ズレる感じはありませんか?
これらの項目にいくつか当てはまる場合は、噛み合わせのズレが生じている可能性があります。
小さなズレでも、放っておくと大きなトラブルの元になることがあるので、早めの確認が大切です。
こんな症状があれば要注意
噛み合わせが乱れていると、思いがけない症状が出ることがあります。
以下のようなサインが現れている場合は、一度歯科医院で噛み合わせのチェックを受けることをおすすめします。
- インプラント周辺の歯ぐきが腫れたり、出血しやすい
- あごが疲れやすい、痛みを感じる
- 頭痛や肩こり、首のこわばりを感じることが増えた
- 食事中に一部の歯だけで噛んでいると感じる
- 朝起きたときにあごに違和感がある
これらの症状は、噛み合わせだけでなく全身のバランスにも関係していることがあります。
見直してみよう!生活習慣と噛み合わせ
日々のちょっとしたクセが、噛み合わせに影響を与えていることもあります。
次のような習慣がないか、振り返ってみてください。
- 片側だけで噛むクセがある
- 寝ている間に歯ぎしり・食いしばりをしている
- 頬杖をつく、うつぶせで寝る、横向きでスマホを見る
- ストレスを感じると無意識に歯に力が入っている
- やわらかいものばかり食べている
これらはすべて、噛み合わせを乱す原因になるクセです。
意識して少しずつ改善していくだけでも、あごや筋肉への負担が減り、インプラントの安定にもつながります。
噛み合わせの不調は、毎日の中で少しずつ進んでしまうもの。
だからこそ「なんとなくおかしいな」と感じたタイミングで、自分でチェックしたり、歯科での診断を受けることがとても大切です。
6.歯科医院で行う噛み合わせ調整とは?
 「インプラントを入れた後、なんだか噛みづらい」「左右どちらかだけで噛んでいる気がする」と感じたことはありませんか?
「インプラントを入れた後、なんだか噛みづらい」「左右どちらかだけで噛んでいる気がする」と感じたことはありませんか?
そんなときに必要なのが、歯科医院で行う「噛み合わせ調整」です。
まずは検査で“今の噛み合わせ”をしっかりチェック
噛み合わせの調整は、まず「どこに問題があるのか」を見つけるところから始まります。歯科医院では次のような検査を行います:
- かみ合わせの接触確認(咬合紙テスト)
→ 噛んだときにどの歯が強く当たっているかを調べる方法です。 - 顎の動きのチェック
→ 顎を開け閉めしたときの動きにズレがないか、痛みがないかを確認します。 - 口腔内スキャンや模型の作製
→ 歯並びや噛み合わせの状態を立体的に再現し、より正確に確認できます。
必要に応じて、CTやレントゲンで骨やインプラントの状態も併せて確認します。
調整の流れと、どれくらい通えばいいの?
噛み合わせの調整は、1回で終わることもあれば、数回に分けて少しずつ行うこともあります。これは、患者様の状態によって異なります。
一般的な流れとしては…
- 検査・カウンセリング └ 現状のかみ合わせや違和感について、詳しくお話を伺います。
- 微調整(インプラントや周囲の歯の高さを調整) └ 特別な器具で咬合面を少しずつ削ったり、調整材を使ってかみ合わせを整えます。
- 経過観察と再調整 └ 実際の生活の中での噛み心地を確認しながら、必要があればさらに調整を加えます。
✅調整には個人差がありますが、数回の通院で安定する方が多いです。
メンテナンスで噛み合わせをキープ
調整が完了したからといって、それで終わりではありません。噛み合わせは、生活習慣や年齢とともに少しずつ変化していくものです。
長く快適にインプラントを使っていただくためにも、定期的なメンテナンスがとても大切です。
- 噛み合わせチェック(3〜6ヶ月ごと)
- クリーニングで周囲の歯や歯ぐきの健康もサポート
- 日常の癖や噛み方のアドバイス
とくに歯ぎしりや食いしばりのある患者様には、マウスピースの使用などもご提案することがあります。
「せっかく入れたインプラントを長持ちさせたい」
「食事や会話をもっと快適に楽しみたい」
そんな想いを叶えるためには、噛み合わせの調整とメンテナンスがとても重要です。
ちょっとした違和感も、「そのうち慣れるだろう」と我慢せず、ぜひ気軽にご相談ください。
7.噛み合わせを整えるための生活習慣
 インプラント治療を受けたあと、噛み合わせのバランスを保つことはとても大切です。
インプラント治療を受けたあと、噛み合わせのバランスを保つことはとても大切です。
でも実は、歯科医院での調整だけでなく、患者様ご自身の毎日の生活習慣が噛み合わせに大きな影響を与えていることをご存じですか?
食いしばり・歯ぎしりを予防するには?
無意識のうちに「食いしばり」や「歯ぎしり」をしている方はとても多いです。特に夜間の歯ぎしりは自覚がなくても、インプラントや周囲の歯に大きな負担をかけてしまいます。
こんな対策がおすすめです:
- 就寝時にマウスピースを使う
歯科医院で作るナイトガードは、歯やインプラントを保護してくれます。 - 日中、ふとしたときに歯を食いしばっていないか意識する
「上下の歯はふだんは触れ合っていないのが正常」なんです。軽く唇を閉じたリラックスした状態を意識しましょう。 - パソコン作業・運転中など集中する場面で要注意
無意識に力が入ってしまいやすいので、深呼吸や軽いストレッチで力を抜いてみてください。
姿勢や噛み癖を見直してみよう
意外かもしれませんが、姿勢や日常の癖も噛み合わせに関係しています。
- 頬杖をつくクセ
→ 顎の位置がズレて、かみ合わせが偏る原因に。 - いつも同じ側で噛む
→ 一方だけの筋肉が発達してバランスが崩れることも。 - 猫背やストレートネック
→ 顎の位置に影響して、噛み合わせが乱れることがあります。
✅できるだけ左右均等に噛むよう意識したり、姿勢を正すことが、噛み合わせの安定につながります。
ストレスと噛み合わせの意外な関係
ストレスを感じると、体は無意識に力が入りやすくなります。その結果、「日中の食いしばり」や「夜間の歯ぎしり」が増えてしまうことも。
ストレスケアの一例:
- 軽い運動やストレッチで身体をリラックス
- しっかり睡眠をとって疲れをためこまない
- 深呼吸や瞑想など、心を落ち着ける時間を意識的に作る
✅ストレスとうまく付き合うことは、噛み合わせだけでなく全身の健康にもプラスになります。
噛み合わせの乱れは、見た目ではわかりにくいものですが、少しずつインプラントやご自身の歯に負担をかけてしまいます。だからこそ、日頃の小さな習慣の積み重ねがとても大切なんです。
8.インプラント治療後の定期メンテナンスの重要性
 インプラント治療が無事に終わったとき、「もう歯医者に通わなくても大丈夫かな」と思われる患者様は意外と多いです。たしかに、治療そのものが終了すれば、ひと安心ですよね。
インプラント治療が無事に終わったとき、「もう歯医者に通わなくても大丈夫かな」と思われる患者様は意外と多いです。たしかに、治療そのものが終了すれば、ひと安心ですよね。
しかし実は、インプラントは治療後こそが“スタート”と言っても過言ではありません。長く快適に使っていただくためには、治療後の定期的なメンテナンスがとても重要なのです。
定期検診でチェックするポイントとは?
インプラントは人工の歯ですから、天然歯のように虫歯になることはありません。
ですが――インプラントを支える歯茎や骨は、患者様ご自身の生きた組織。お手入れが不十分だと、炎症を起こしてしまったり、最悪の場合、インプラントがグラグラして抜けてしまうこともあります。
以下のような点を、定期検診でしっかりチェックしていきます:
- インプラント周囲の歯茎に炎症や出血がないか
- 噛み合わせのバランスが崩れていないか
- インプラントのネジや被せ物にゆるみや破損がないか
- 他の歯との接触関係(咬合調和)が保たれているか
✅少しの違和感でも、専門的な目で早めに見つけて対処すれば、トラブルは未然に防げます。
噛み合わせ調整のタイミングって?
治療が終わった直後はバランスが取れていても、時間とともに噛み合わせは少しずつ変化していくことがあります。
その原因は様々ですが、たとえば──
- 周囲の天然歯がすり減ったり動いたりする
- 顎の筋肉の使い方が変わる(食事や会話、クセの影響)
- 片側ばかりで噛むなど、日常の習慣の積み重ね
こうした変化をそのままにしてしまうと、インプラントに余計な力が加わり、周囲の歯や顎関節にまで影響する可能性があります。
✅定期的な噛み合わせのチェックと調整で、インプラントへの負担を軽減し、快適さを長く保てます。
インプラントを長く快適に使うためのメンテナンス方法
インプラントは「つけて終わり」ではありません。
大切なのは、その後どう守っていくか。それによって、快適な使用期間も大きく変わってきます。
以下のような習慣を意識してみましょう:
- 3〜6か月に1回は定期検診を受ける
- 毎日の歯磨きを丁寧に行い、正しいブラッシング法を習得する
- 歯間ブラシやデンタルフロスで、インプラントの周りもきちんと清掃
- 少しでも違和感があれば、自己判断せずすぐに歯科医院へ相談
また、歯科医院で行うプロフェッショナルクリーニングでは、目に見えない「バイオフィルム(細菌の膜)」までしっかり除去できます。
これが、インプラント周囲炎の予防にとても効果的なんです。
「入れたら終わり」ではなく、「一緒に育てていく」──そんな気持ちで、ぜひ今後のメンテナンスにも取り組んでいきましょう。
9.インプラントを長持ちさせるためのセルフケア
 インプラントは天然の歯と違って「虫歯」にはなりませんが、周囲の歯茎や骨はご自身の組織です。
インプラントは天然の歯と違って「虫歯」にはなりませんが、周囲の歯茎や骨はご自身の組織です。
そのため、毎日のセルフケアがきちんとできているかどうかで、インプラントの寿命も大きく変わってきます。
正しいブラッシング方法を身につけましょう
インプラントは天然の歯と構造が少し異なるため、磨き方にも工夫が必要です。
✅インプラント周囲をケアするポイント:
- 毛先のやわらかい歯ブラシを使う(インプラント周辺をやさしく清掃できます)
- インプラントの根元にブラシを斜め45度であてて、小刻みに動かす
- 力を入れすぎないことが大切(強くこすりすぎると、歯茎を傷める原因になります)
- 歯と歯の間は、デンタルフロスや歯間ブラシを併用するとより効果的です
特に、インプラント周囲にプラーク(歯垢)がたまると、インプラント周囲炎という病気につながるリスクがあるため、日々の丁寧なケアが最も大事なんです。
インプラントに優しい食生活も意識して
噛む力のバランスを保つためには、「よく噛んでゆっくり食べる」ことが基本です。
急いで食べたり、片側ばかりで噛んだりすると、インプラントや周囲の歯に過度な力がかかり、噛み合わせが乱れる原因になります。
こんな食習慣を意識してみましょう:
- 硬すぎる食べ物は避ける(氷・骨付き肉・硬いおせんべいなど)
- 左右均等に噛むことを意識する
- 繊維質のある野菜や噛み応えのある食材で筋肉をバランスよく使う
また、甘いお菓子や糖分が多いジュースなどは、インプラント周囲の細菌の増殖を助けてしまうことも。
適度な摂取と、食後の丁寧なブラッシングを心がけましょう。
口腔内を健康に保つための生活習慣
セルフケアは「歯磨き」だけではありません。実は、日々の生活習慣すべてが口の健康に関係しているんです。
以下のような習慣を意識することで、インプラントだけでなく、お口全体の健康維持につながります:
- 夜更かしを避けて、質の良い睡眠をとる
- ストレスをためすぎない(歯ぎしりや食いしばりの予防にもなります)
- 禁煙または減煙を意識する(喫煙は歯茎の血流を悪くし、インプラント周囲炎のリスクを高めます)
- 水分をしっかりとる(唾液が口の中を清潔に保つ働きをしてくれます)
また、「定期的な歯科検診」もセルフケアの一環と考えていただけると良いと思います。ご自身では見えにくい場所のチェックや、細かい調整が必要な場合もあります。
インプラントは、正しく使えば10年、20年と長く活躍してくれる優れた治療法です。
そのためにも、毎日のちょっとした習慣や意識が大きな差を生みます。
「治療が終わったら終わり」ではなく、「治療後こそが大切なスタート」。
10.よくある質問
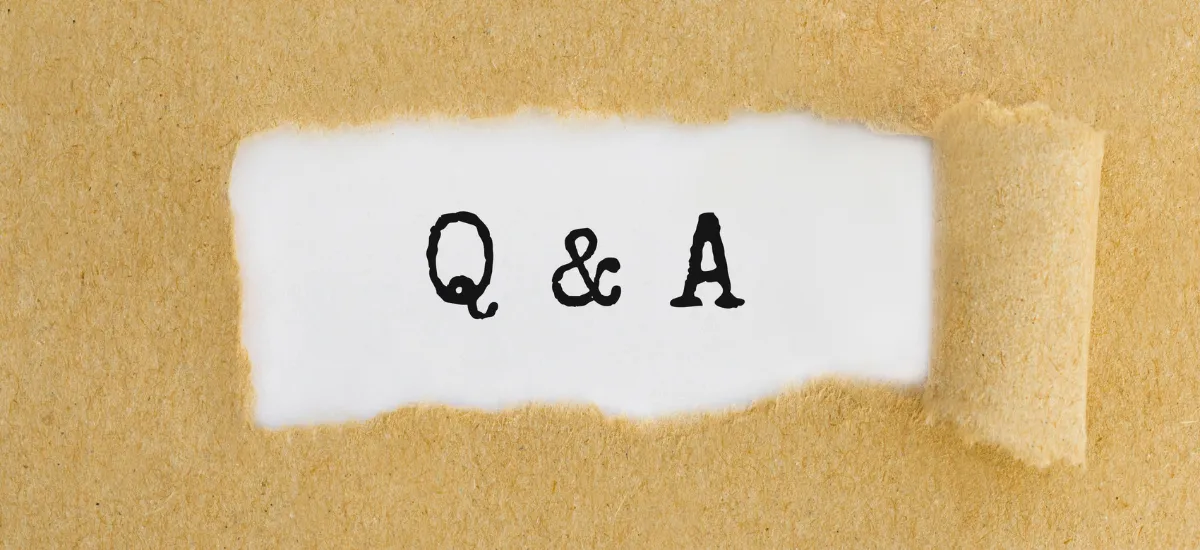 インプラント治療後、「噛み合わせが少し気になる」「違和感があるけど大丈夫?」というご相談をいただくことがあります。
インプラント治療後、「噛み合わせが少し気になる」「違和感があるけど大丈夫?」というご相談をいただくことがあります。
治療が終わった後こそ、日々のケアやちょっとした変化に気づくことがとても大切です。
Q1:噛み合わせが合わないと感じたら、どうすればいい?
A1:まずは我慢せず、できるだけ早く歯科医院へご相談ください。
治療直後は、慣れるまで少し時間がかかることもありますが、
- 食事のときに片側だけで噛んでしまう
- 顎が疲れる・痛い
- 歯がぶつかる感覚がある
などの違和感が続く場合は、噛み合わせがズレている可能性があります。
放っておくと、顎関節に負担がかかったり、インプラントの寿命に影響することもあるため、
「少し変かも?」と思った段階で、遠慮なくご連絡くださいね。
Q2:調整にはどれくらいの期間がかかりますか?
A2:調整そのものは1回の通院で済むこともありますが、状態によって異なります。
例えば、
- 少しの噛み合わせの高さ調整なら10〜15分ほど
- 咬合(こうごう)状態の変化が大きい場合や、複数のインプラントが関係する場合は数回の調整が必要なこともあります。
違和感を我慢して噛み続けてしまうと、せっかくのインプラントに負担がかかってしまうので、早めの対応がとても大切です。
Q3:定期的なチェックはどのくらいの頻度で必要ですか?
A3:目安としては、半年に1回の定期検診がおすすめです。
ただし、以下のような方は3ヶ月に1回程度のチェックが安心です:
- 歯ぎしり・くいしばりの癖がある方
- インプラント以外にも治療済みの歯が多い方
- 歯周病のリスクが高い方(糖尿病・喫煙など)
定期検診では、
- 噛み合わせのチェック
- インプラント周囲の炎症の有無
- 歯磨きの状態(セルフケア)
などを確認し、必要があればその場で調整も行います。
✅インプラントは「入れて終わり」ではなく、「使いながら守る」治療です。
気になることは些細なことでも遠慮せずにお話しいただくのが、長持ちさせる秘訣です。
インプラントは、見た目や噛む力を取り戻すだけでなく、毎日の生活を豊かにしてくれる素晴らしい治療法です。
ですが、その効果をしっかり発揮し、長持ちさせるためには「噛み合わせのバランス」がとても大切なカギになります。
治療後にちょっとした違和感があったり、噛みづらさを感じたりするのは、決して珍しいことではありません。
そんな時こそ、ご自身の感覚を大切にしながら、遠慮せずに歯科医師へご相談ください。
東京都品川区YDC精密歯周病インプラント治療専門ガイド
監修:医療法人スマイルパートナーズ 理事長/齋藤和重
『山手歯科クリニック大井町』
住所:東京都品川区東大井5丁目25−1 カーサ大井町 1F
『山手歯科クリニック戸越公園』
住所:東京都品川区戸越5丁目10−18
*監修者
*経歴
1990年 鶴見大学歯学部卒業。1991年 インプラント専門医に勤務。1999年 山手歯科クリニック開業。
2001年 INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS卒業。
2010年 医療法人社団スマイルパートナーズ設立。
*所属
・ICOI国際インプラント学会 指導医
・ICOI国際インプラント学会 ローカルエリアディレクター
・ITI国際インプラント・歯科再生学会 公認 インプラントスペシャリスト
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本顎顔面インプラント学会 会員
・国際審美学会 会員
・日本歯科審美学会 会員
・日本アンチエイジング歯科学会 会員
・INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS(2001年)
・CID Club (Center of Implant Dentistry)所属
・国際歯周内科研究会 所属
・5-D JAPAN 所属
・デンタルコンセプト21 所属
・インディアナ大学歯学部 客員 講師
・南カルフォルニア大学(USC)客員研究員
・南カルフォルニア大学(USC)アンバサダー
・USC (南カルフォルニア大学)歯学部JP卒
・USC University of Southern California)センチュリー・クラブ
・プレミアム・メンバー
※詳しいプロフィールはこちらより

