歯周病の原因、磨き残しだけ?知られざるバイオフィルムの正体とは?
こんにちは。スマイルパートナーズ山手歯科クリニックです。
皆さんはバイオフィルムという存在をご存じですか?バイオフィルムとは、細菌が作るネバネバした膜状のかたまりで、私たちの目には見えないものの、歯や歯茎にしっかりとへばりつき、歯周病や口臭の大きな原因になります。
しかもこのバイオフィルム、通常の歯磨きでは完全に落とすことができないという厄介な特徴が…。そのまま放置していると、歯周病が進行したり、全身の健康にも影響を与える可能性があるのです。
今回は、「バイオフィルムとは何か?」「なぜ歯周病を引き起こすのか?」「どうすれば効果的に除去できるのか?」といった疑問にお答えしていきます。
毎日のケアでは防げない“見えないリスク”にしっかり備えるために、ぜひチェックしてみてください。
1.こんなお悩み、ありませんか?
 「ちゃんと歯磨きしているのに、なんで歯ぐきが腫れるんだろう…」
「ちゃんと歯磨きしているのに、なんで歯ぐきが腫れるんだろう…」
「口臭が気になるけれど、原因が思い当たらない…」
「歯石取りもしてるのに、歯周病って言われてしまった…」
実は、こうしたお悩みをお持ちの患者様はとても多くいらっしゃいます。
毎日きちんと歯を磨いて、歯科にも通っているのに、なぜ歯周病になってしまうのか――その原因のひとつに、「バイオフィルム」という存在が関係していることをご存じでしょうか?
バイオフィルムとは、お口の中の細菌たちが集まって作るネバネバした膜のこと。
この膜が、歯の表面や歯と歯ぐきの境目にこっそりとたまり、目には見えないところで歯周病を進行させてしまうことがあるのです。
どんなに丁寧に磨いても、歯ブラシだけでは落としきれないこのバイオフィルム。
放っておくと、歯ぐきの炎症や出血、さらには歯を支える骨にまで悪影響を与える恐れがあります。
「磨いているのに、なぜ?」という疑問の裏には、
“バイオフィルム”という見えない敵が潜んでいるかもしれません。
2.バイオフィルムとは? 歯周病の“かくれた原因”に要注意!
 「毎日ちゃんと歯を磨いているのに、どうして歯ぐきが腫れる?」
「毎日ちゃんと歯を磨いているのに、どうして歯ぐきが腫れる?」
「定期的に歯石も取っているのに、歯周病って言われた」
その“原因のひとつ”として、見逃せないのが 「バイオフィルム」の存在です。
バイオフィルムって何?
簡単に言えば、お口の中の細菌たちがつくる「ネバネバの膜」のことです。
この膜の中には、歯周病や虫歯の原因となる悪い細菌がびっしり住み着いていて、
歯の表面や歯ぐきのまわりにベッタリと貼りついているのが特徴です。
バイオフィルムは、一度できてしまうと、
歯ブラシではなかなか落とすことができないというやっかいな存在。
しかも、うがいや市販の洗口剤でも届かず、薬も効きにくい構造になっているんです。
「プラーク」との違いは?
「それって、プラーク(歯垢)のことですか?」というご質問も多いです。
実は、バイオフィルムとプラークはとても近い関係にあります。
- プラーク:歯に付着したやわらかい細菌のかたまり(磨き残し)
- バイオフィルム:そのプラークが時間をかけて進化し、膜状になったもの
つまり、プラークを放置していると、やがてバイオフィルムになってしまうというわけです。
このバイオフィルムこそが、歯周病の進行に深く関係しています。
なぜバイオフィルムが問題なのか?
見た目には透明で気づきにくいバイオフィルム。ですが、問題点はたくさんあります。
- ✅薬や唾液が届きにくいバリア構造になっている
- ✅細菌が守られて繁殖しやすい環境をつくっている
- ✅時間が経つと歯石に変わり、さらに取りにくくなる
- ✅歯ぐきの腫れ・出血・口臭・歯のぐらつきなどを引き起こす
特に歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)にバイオフィルムが溜まると、
歯周病が気づかないうちにどんどん進行してしまうことがあるのです。
毎日の歯磨きでは取り切れない?
残念ながら、バイオフィルムはセルフケアだけでは完全に除去できないことがほとんどです。
どんなにていねいに磨いていても、
歯ブラシの毛先が届きにくい部分に蓄積し、強力にこびりついてしまいます。
このため、歯科医院でのプロによるクリーニングがとても重要になります。
バイオフィルムは、いわば「歯周病菌のすみか」です。
見た目には分かりづらくても、お口の健康をむしばむ大きな要因となります。
「毎日磨いているのに不調が続く」
「定期的に歯石を取っているのに歯ぐきが腫れる」
そんなときは、バイオフィルムの存在を疑ってみてもいいかもしれません。
定期的なメンテナンスで取り除くことで、歯周病の予防や改善に大きな効果が期待できます。
3.バイオフィルムが歯周病を引き起こす理由
 「バイオフィルムって聞いたことはあるけど、何がそんなに問題なの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
「バイオフィルムって聞いたことはあるけど、何がそんなに問題なの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
実はこのバイオフィルム、歯周病の“はじまり”をつくる非常に厄介な存在なんです。
ネバネバの正体は、細菌の“シェルター”
バイオフィルムとは、細菌たちが集まって、自分たちを守るために作ったネバネバした膜のことです。
歯の表面、歯ぐきのすき間、被せ物の周りなど、あらゆる場所にくっついています。
この膜はとても強力で、
- ✅歯ブラシの毛先が届きにくい
- ✅ 薬や洗口剤が中に入りにくい
- ✅細菌が外敵から守られ、繁殖しやすい
…という特徴があります。
この状態が続くと、バイオフィルムの中でどんどん悪い細菌が増え、
やがて歯ぐきに炎症を起こす=歯周病が始まるのです。
歯茎の炎症が進んでいくメカニズム
歯周病は、最初は「歯ぐきの軽い腫れや出血」など、気づかれにくい症状から始まります。
でもその裏では、バイオフィルム内の細菌がじわじわとダメージを広げているんです。
✔ バイオフィルムが歯と歯ぐきのすき間にたまる
↓
✔ 細菌が毒素を出し、歯ぐきが炎症を起こす
↓
✔ 炎症が慢性化すると、歯を支える骨が溶け始める
つまり、バイオフィルムがある限り、炎症は止まらず進行してしまうのです。
免疫力が下がるとどうなるの?
健康なときは、体の免疫力がこの炎症にある程度対応してくれます。
でも、風邪をひいているとき、睡眠不足が続いているとき、糖尿病などの持病があるときには注意が必要です。
- ✅免疫力が落ちると細菌に対抗できず、炎症が急速に進行
- ✅治療しても再発しやすくなる
- ✅慢性的に歯ぐきが腫れたり、出血が止まらなかったりする
「なんだか最近、歯ぐきの調子が悪いな…」というときは、体のコンディションも関係しているかもしれません。
毎日磨いているつもりでも、
バイオフィルムが残っていれば、歯周病は少しずつ進んでしまうことがあります。
しかも初期はほとんど自覚症状がないため、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。
バイオフィルムをしっかり落とすには、プロによるメンテナンスが不可欠です。
4.バイオフィルムはどうやってできる?
 患者様からよくいただく質問のひとつが「バイオフィルムって、いったいどこから出てくるんですか?」というものです。
患者様からよくいただく質問のひとつが「バイオフィルムって、いったいどこから出てくるんですか?」というものです。
バイオフィルムは、実は毎日の生活の中で、気づかないうちに少しずつできているんです。
どれくらいの時間でできるの?
バイオフィルムは、食後わずか数時間で歯の表面に作られ始めます。
「えっ、そんなに早いの?」と思われるかもしれませんが、私たちの口の中には常に何百種類もの細菌が存在していて、食べかすや糖分をエサにして活動しています。
特に、次のような条件がそろうとあっという間にバイオフィルムが形成されてしまいます。
- 歯みがきを忘れた
- 磨き残しがあった
- だらだら食べて口の中に糖分が残っていた
つまり、「夜しっかり磨いたから今日は大丈夫!」と思っても、翌朝にはもうバイオフィルムができ始めているということもあるんです。
食生活との関係って?
バイオフィルムの成長には、食べる内容や回数も深く関係しています。
とくに注意が必要なのが「砂糖」や「やわらかい食べ物」が多い食生活です。
✅バイオフィルムができやすい食習慣の例:
- 甘い飲み物やお菓子をちょこちょこ摂る
- ごはんやパンなどの炭水化物中心の食事が多い
- よく噛まずにサッと飲み込むクセがある
このような食習慣では、細菌のエサとなる糖分が口の中に長く残るため、バイオフィルムがどんどん厚くなっていきます。
逆に、繊維質の多い野菜やよく噛んで食べる習慣は、唾液の分泌を促して自浄作用を高めるのでおすすめです。
唾液の量もカギになります!
実は、バイオフィルムが増えやすいかどうかは、唾液の量や質にも大きく関係しています。
唾液には本来、「細菌を洗い流す」「殺菌する」「酸を中和する」といった働きがあります。
でも、唾液が減ってしまうと…
- ✔口の中が乾燥して細菌が繁殖しやすくなる
- ✔食べかすが流されにくくなる
- ✔酸がたまりやすく、歯や歯ぐきに負担がかかる
こういった状態が続くと、バイオフィルムがより強力になって歯周病リスクが一気に高まるんです。
ちなみに、加齢・ストレス・薬の副作用・口呼吸なども唾液の分泌量に影響するので、気になる方は一度ご相談くださいね。
バイオフィルムは目に見えないだけに、油断するといつの間にかたまっていることが多いです。
だからこそ、
- 毎日のセルフケア(丁寧な歯みがき・フロスなど)
- 食生活や唾液分泌を意識する
- 歯科医院での定期的なチェックとクリーニング
この3つがとても大事です。
次の章では、バイオフィルムを取り除くために歯科医院でできることについて、詳しくお話していきます。歯周病予防の第一歩として、ぜひ知っておいてくださいね。
5.バイオフィルムを放置するとどうなる?
 「バイオフィルムって、そんなに悪いものなんですか?」見た目にはあまりわからないこの“ネバネバした細菌の膜”ですが、放っておくとお口の中だけでなく、体全体の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるんです。
「バイオフィルムって、そんなに悪いものなんですか?」見た目にはあまりわからないこの“ネバネバした細菌の膜”ですが、放っておくとお口の中だけでなく、体全体の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるんです。
歯周病の進行がどんどん進んでしまう
まず一番大きなリスクは、やはり歯周病の悪化です。
バイオフィルムの中には、歯ぐきに炎症を起こす細菌がたくさんひそんでいます。この細菌が長く停滞することで、こんな変化が起きます。
✅歯ぐきが赤く腫れる、血が出る
✅歯と歯ぐきの間に深いポケットができる
✅骨が徐々に溶けていく
最終的には歯がグラグラし、抜けてしまうことも…
このように、初期の軽い症状からあっという間に重度の歯周病へ進行してしまうこともあります。
全身疾患との関係にも注意
歯周病はお口だけの病気と思われがちですが、実は全身の病気とも深い関わりがあることがわかってきています。
バイオフィルム中の細菌が血液を通じて全身にまわると、以下のような疾患のリスクを高めるとされています。
✅心筋梗塞や脳梗塞などの血管系の病気
✅誤嚥性肺炎
✅糖尿病の悪化
✅早産・低体重児出産 など
特に、糖尿病や高血圧をお持ちの患者様は要注意です。
お口の中のバイオフィルムが、知らない間に全身の健康を脅かすきっかけになっているかもしれません。
「気づいたら歯が抜けていた」なんてことも…
バイオフィルムは、歯の根っこの周りにじわじわと炎症を広げていきます。
しかも、痛みがあまりないまま進行することも多いため、「気づいたときには手遅れだった…」というケースも珍しくありません。
患者様の中には、
- 「毎日歯を磨いていたのに、なぜか歯がグラグラして…」
- 「痛くないから様子を見ていたら、歯が抜けてしまった…」
というご経験をされた方もいらっしゃいます。
歯を失うと、噛む力が弱くなり、食事が楽しめなくなるだけでなく、発音や見た目の印象にも影響します。
ご自身の歯を1本でも長く守るために、バイオフィルムの管理はとても重要なんです。
バイオフィルムは、毎日の歯磨きでは完全に取りきるのが難しいため、知らないうちにどんどんたまってしまうものです。
「特に痛みもないし、大丈夫かな?」と油断していると、歯周病や全身への影響がじわじわと進んでいることもあります。
6.毎日の歯磨きだけではバイオフィルムは落とせない?
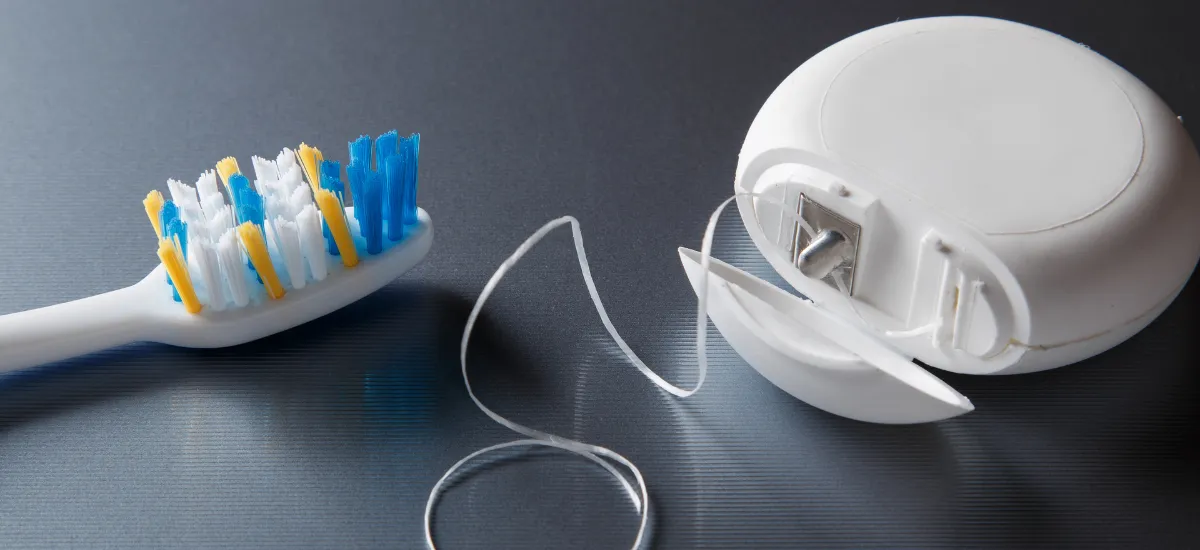 「ちゃんと歯を磨いているのに、どうして歯周病って言われるんだろう…」
「ちゃんと歯を磨いているのに、どうして歯周病って言われるんだろう…」
歯磨きはもちろん大事ですが、実は“あるもの”が原因で、それだけでは不十分なケースがあるのです。
その“あるもの”というのが、そう、バイオフィルムです。
バイオフィルムは、簡単には落ちないネバネバ膜
バイオフィルムというのは、細菌たちが歯の表面にくっついて、まるで“バリア”のようなネバネバした膜を作っている状態のこと。
この膜、実はとてもやっかいで、
✅歯ブラシの毛先が届いても“こすったくらい”では落ちにくい
✅水やうがいでは流れない
✅しかも、時間がたつほど厚く強固になっていく
という特徴があります。
見た目にはツルっとしていても、バイオフィルムの中では細菌たちが活発に活動している状態なのです。
歯周病や虫歯の温床になることも…
このバイオフィルム、放っておくと中で増殖した細菌たちが、
✅歯ぐきに炎症を起こす(歯肉炎)
✅骨を溶かす(歯周病)
✅酸を出して歯を溶かす(虫歯)
といった悪さを始めてしまいます。
しかも、1日程度で再形成されてしまうため、毎日のケアで取り除けなければ、あっという間に歯周病が進行してしまうことも。
歯間ブラシ・デンタルフロスで届かない場所をケア
バイオフィルムは特に、
- 歯と歯の間
- 歯と歯ぐきの境目
- 奥歯の裏側
など、“歯ブラシが届きにくい場所”にたまりやすいです。
そのため、歯ブラシだけでは不十分なんですね。
そこで活躍するのが、
✅歯間ブラシ:歯と歯のすき間に差し込んで汚れを落とす
✅デンタルフロス:細い糸で歯と歯の間のバイオフィルムを除去する
という補助的な道具です。
これらを毎日のケアにプラスすることで、歯ブラシだけでは落としきれないバイオフィルムも取り除くことが可能になります。
除去のポイントは「力よりも丁寧さ」
「じゃあゴシゴシ強く磨けばいいの?」と思われるかもしれませんが、
力任せに磨くと、歯ぐきを傷つけてしまう恐れがあります。
大切なのは、
✅軽い力で、小刻みに動かす
✅歯の表面だけでなく、歯と歯ぐきの境目にも毛先を当てる
✅歯間ブラシは無理に入れず、自分のすき間のサイズに合ったものを使う
という「丁寧なケア」です。
時間をかけすぎなくても、毎日数分の正しいケアを積み重ねることで、バイオフィルムはかなり防ぐことができます。
毎日しっかり歯磨きしていても、それだけではバイオフィルムは完全には落とせないことも多いんです。
そのため、
- 歯間ブラシやフロスなどの補助的な道具を活用する
- プロの手による定期的なクリーニングを受ける
- バイオフィルムがつきやすい場所を知ってケアする
といった“ちょっとした工夫”の積み重ねが、お口の健康を守る大きな力になります。
歯周病や虫歯になってからではなく、“なる前の予防”こそが何よりも大切です。
7.バイオフィルムの徹底除去!歯科医院でのプロフェッショナルケア
 「毎日しっかり歯を磨いているのに、どうして歯周病になるの?」
「毎日しっかり歯を磨いているのに、どうして歯周病になるの?」
そんなふうに感じたことはありませんか?
実は、歯磨きだけではどうしても落としきれない汚れがあるんです。
その代表が「バイオフィルム」と呼ばれる、歯の表面や歯ぐきの境目にこびりついた細菌の膜。
このバイオフィルムは、歯科医院でのプロフェッショナルケアでこそ、しっかり除去することができます。
PMTC(プロフェッショナルクリーニング)ってなに?
PMTCとは、「プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング」の略。
つまり、専門の器械と技術を使って、歯科衛生士が行う本格的なお口のクリーニングです。
こんな効果があります:
✅バイオフィルムを徹底的に除去できる
✅歯の表面がツルツルになり、汚れがつきにくくなる
✅歯ぐきの炎症をやわらげ、歯周病を予防
普段の歯磨きでは届かない奥の部分や歯ぐきの内側など、プロならではの視点で細かく丁寧にケアしていきます。
超音波スケーラーのパワーとは?
バイオフィルムが長期間放置されると、やがて「歯石」へと変化します。
この歯石はとても硬く、普通のブラッシングではまず取れません。
ここで登場するのが「超音波スケーラー」。
これは、微細な振動と水流で、歯の表面や歯周ポケット内の歯石やバイオフィルムを優しく取り除く機器です。
✅痛みが少なく、短時間で効率的
✅歯ぐきの中までキレイにできる
✅細菌の温床を根本から断つ
といった特徴があり、歯周病の予防や改善には欠かせないツールです。
定期メンテナンスの重要性
「治療が終わったから、もう通わなくていいかな」と思われる方も多いですが、
実はそこからが本番です。
インプラントや天然歯を問わず、お口の健康を維持するには“定期的なメンテナンス”がカギになります。
- メンテナンスでチェックすること:
- 歯ぐきの腫れや出血の有無
- バイオフィルムや歯石の再付着
- 噛み合わせのバランス
- 日々のセルフケアの見直しポイント
こうしたチェックを3〜6ヶ月に1回のペースで受けることで、
トラブルを未然に防ぎ、健康な歯ぐきをキープできます。
バイオフィルムは、放っておくと歯ぐきに炎症を起こし、やがて歯周病を進行させてしまいます。
ですが、正しいセルフケアと、歯科医院でのプロフェッショナルケアを組み合わせれば、しっかりコントロールできるのです。
「定期的に通うのは大変だな」と思われるかもしれませんが、
ほんの数ヶ月に一度のチェックとクリーニングが、何十年先の歯の健康を守ってくれると思えば、とても意味のある時間だと思います。
8.バイオフィルムの形成を防ぐセルフケアのポイント
 歯周病の大きな原因のひとつ「バイオフィルム」。
歯周病の大きな原因のひとつ「バイオフィルム」。
これは、ただの汚れではなく、細菌が集まってつくり出す“ネバネバの膜”のようなものです。
とてもやっかいな存在で、毎日の歯磨きだけでは完全に取りきれないことも多いのですが、実は日々のちょっとした工夫や意識で、その“つきにくさ”をグッと下げることができるんです。
正しいブラッシング方法と歯ブラシの選び方
まずはやはり、基本となるのは歯磨きです。
毎日なんとなく磨いているつもりでも、力の入れすぎで歯ぐきを傷つけていたり、磨き残しが多かったりすることは珍しくありません。
✅ブラッシングのポイント
- 歯ブラシはやわらかめ〜ふつうの毛で、小さめのヘッドを選びましょう
- 歯と歯ぐきの境目に毛先を斜め45度に当てる
- ゴシゴシではなく、軽い力で小刻みに磨く(1本ずつ丁寧に)
- 歯磨き時間は最低でも2分以上が理想です
歯ブラシの交換は1ヶ月に1回が目安。毛先が開いたら即チェンジしましょう!
歯ブラシだけじゃ足りない?補助アイテムも活用を
バイオフィルムは、歯と歯の間や奥歯の裏側など、細かいところにたまりやすいです。
そこで、補助清掃具の出番です。
- デンタルフロス:歯と歯のすき間に入れて、歯ぐきのキワまできれいに
- 歯間ブラシ:歯の間が広めの方におすすめ。根元の汚れを除去できます
- ワンタフトブラシ:奥歯や親知らずの周りに◎
毎日フロスを使うだけでも、歯周病リスクがぐんと減るというデータもあります。
ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、習慣にしてしまえば意外と続きますよ。
食生活と生活習慣の見直しも大切です
バイオフィルムの形成には、お口の中の環境が大きく関係しています。
✅こんな生活習慣は見直しのチャンス!
- 甘いものや間食が多い → 細菌のエサが増えてしまいます
- 寝る前に食べる・飲む → 寝ている間は唾液が減るため、細菌が繁殖しやすい状態に
- 水分不足・口呼吸 → 口の中が乾燥すると、細菌が活発に!
バランスの良い食事、水分補給、口呼吸を鼻呼吸に変える工夫も意識してみましょう。
唾液のチカラを味方にしよう!
唾液には、細菌の増殖を抑えたり、口の中を洗い流したりする作用があります。
つまり、唾液がしっかり出ているだけで、バイオフィルムをつきにくくしてくれるんです。
✅唾液を増やすポイント
- ガムを噛む(キシリトール入りがおすすめ)
- よく噛んで食べる(1口30回を目安に)
- 唾液腺マッサージをしてみる
- 水分をこまめにとる(できればお水)
特にお口が乾きやすい方は、こまめな水分補給と意識的な“噛む”行動がカギになります。
バイオフィルムは、知らず知らずのうちにできてしまうもの。
でも、日々の積み重ねで予防は可能です。
9.バイオフィルムと全身の健康との関係
 「歯周病はお口の中だけの病気」と思っていませんか?
「歯周病はお口の中だけの病気」と思っていませんか?
実は、歯周病の原因である“バイオフィルム”は、放っておくと全身の健康にも深く関わってくることがわかってきています。
私たち歯科医師が「歯磨きをしっかり」「定期的に通院を」とお伝えするのは、
お口の健康だけでなく、体全体の健康を守るためでもあるんです。
歯周病が引き起こす全身疾患のリスク
バイオフィルムは、ただの汚れではありません。
細菌の塊であり、その一部が歯ぐきの血管から全身へと入り込む可能性があるんです。
この細菌や毒素が血流に乗って巡ることで、以下のような病気との関係が報告されています。
✅糖尿病
- 歯周病があると、血糖値が上がりやすくなることがわかっています。
- 炎症物質がインスリンの働きを邪魔し、コントロールが難しくなることも。
- 一方で、歯周病を治療すると血糖値が改善する例も多く見られます。
✅心筋梗塞・脳梗塞
- 血管内に入り込んだ歯周病菌が、動脈硬化を進行させるといわれています。
- 結果として、血管が詰まりやすくなり、心疾患や脳血管疾患のリスクが高まります。
✅誤嚥性肺炎
- 特に高齢の患者様に多いのがこの病気。
- お口の中の細菌を誤って気道に入れてしまうことで、肺炎を引き起こすことがあります。
- バイオフィルムのケアは、高齢期の健康維持にもつながるんです。
免疫力とお口の環境は深くつながっている
お口の中は、実は体の中でもっとも多くの細菌が存在する場所です。
だからこそ、バイオフィルムを放置すると、免疫がずっと「戦闘態勢」を取り続けなければならず、
結果として体全体の免疫力が下がってしまうこともあるのです。
- 風邪をひきやすくなる
- 疲れやすい、回復が遅い
- 持病が悪化しやすくなる
こうした不調の一部には、お口の細菌バランスが影響している可能性もあるのです。
健康寿命を延ばすための“オーラルケア”
「健康寿命」という言葉をご存知ですか?
ただ生きるだけでなく、元気で自立した生活を送れる期間のことを指します。
この健康寿命を延ばすうえで、実は「お口の健康」がとても大切なんです。
✅健康なお口は、健康な体を支える基盤
- よく噛める=消化が良くなり、栄養がしっかり吸収される
- 食事が楽しい=食欲が出て、免疫力アップ
- しっかり話せる・笑える=人とのつながりが増え、心の健康にも◎
そして、それらを守るためには「バイオフィルムのコントロール」が欠かせません。
バイオフィルムは、放置してしまうと歯周病を進行させ、やがては体全体の健康にも悪影響を与えることがあるということ。
でも、逆に言えば――お口を整えることが、全身の健康への近道になるということでもあります。
10.よくある質問
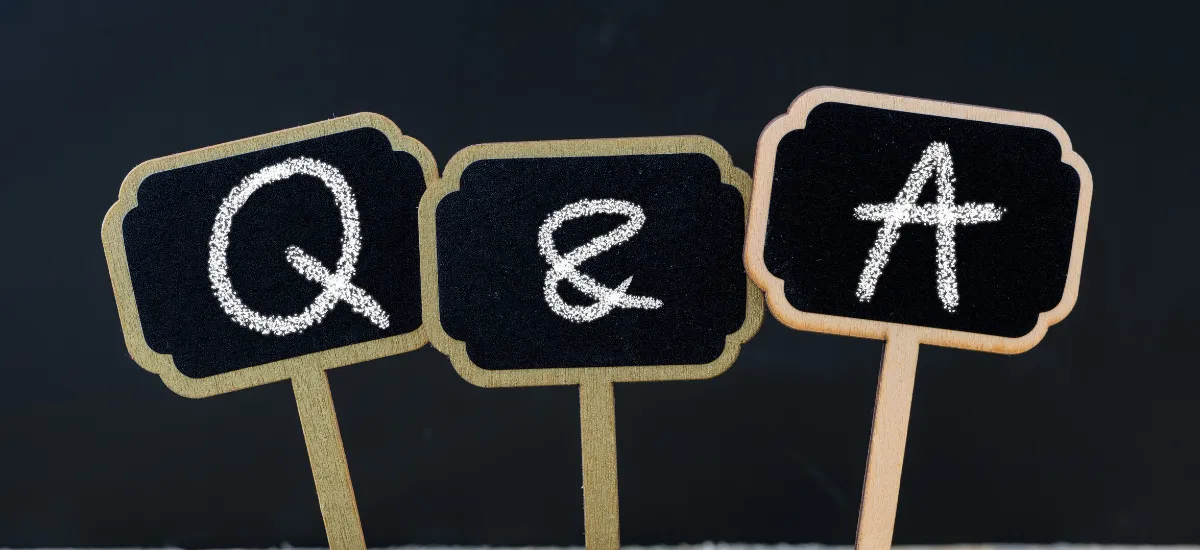 バイオフィルムについてお話しすると、患者様からよくいただくご質問があります。
バイオフィルムについてお話しすると、患者様からよくいただくご質問があります。
「毎日歯を磨いてるのに、なぜできるの?」「自然になくなることはないの?」
今回は、そんな疑問にひとつずつ、わかりやすくお答えしていきますね。
Q1.「毎日歯磨きをしているのにバイオフィルムはできるの?」
A1.はい、どんなに丁寧に磨いていても、バイオフィルムは少しずつ作られてしまいます。
バイオフィルムは、細菌が自分たちでネバネバした膜を作りながら、歯の表面にしっかりと付着している状態のこと。
この膜はとても粘着力が強く、普通の歯磨きでは完全には落としきれないことが多いんです。
特に、
- 奥歯の裏側
- 歯と歯ぐきの境目
- 歯と歯の間
こういった場所には歯ブラシの毛先が届きにくく、知らない間にバイオフィルムが蓄積しやすくなっています。
Q2.「バイオフィルムは自然に消えることはあるの?」
A2.残念ながら、自然に消えることはありません。
バイオフィルムは、水でゆすいだくらいでは落ちませんし、時間が経つほど細菌が増えてどんどん成熟した状態になっていきます。
ある程度まで進行すると、
- 歯周病菌が増殖しやすくなる
- 炎症が強くなりやすい
- 歯石に変わってさらに取りにくくなる
といった悪循環に入ってしまいます。
ですので、日々のセルフケア+定期的なプロのケアがとても大切になってくるんです。
Q3.「定期的に歯科医院に通えば、バイオフィルムは完全に防げるの?」
A3.正直に申し上げると、「完全にゼロにすることは難しい」です。
なぜなら、お口の中には常に細菌が存在しており、バイオフィルムは数時間〜数日で再び形成されてしまうからです。
でもご安心ください。
大切なのは「増やさないこと」「成熟させないこと」なんです。
✅できるだけ毎日の歯磨きで取り除く
✅歯間ブラシやフロスで、歯と歯のすき間もケアする
✅定期的なクリーニングで、残った汚れや歯石をリセット
この3つをしっかり行えば、歯周病のリスクは大きく減らすことができます。
Q4.「バイオフィルム対策におすすめのグッズや方法はある?」
A4.はい、いくつかおすすめのケア方法があります。
- やわらかめの歯ブラシでやさしく、でも丁寧にブラッシング
- 歯間ブラシやフロスで、歯と歯のすき間の汚れも忘れずに
- 電動歯ブラシも、正しい使い方をすれば効果的
- 毎日のうがいに殺菌作用のあるマウスウォッシュを使うのも◎
また、定期的なPMTC(プロフェッショナルクリーニング)も取り入れると安心です。
バイオフィルムは、目には見えないけれど確実に歯の表面に存在していて、放っておくと歯周病やさまざまな全身疾患のリスクを高めてしまう、いわば“静かな敵”です。
「毎日歯を磨いているのに歯ぐきが腫れる」「口臭が気になる」
そんな小さなサインが、バイオフィルムによるお口のトラブルの始まりかもしれません。
ですがご安心ください。
バイオフィルムは、正しいセルフケアと、歯科医院でのプロフェッショナルケアのダブルアプローチで、しっかり予防・管理ができます。
「歯を守ることは、体を守ること」
これからも、一緒に健康なお口づくりを目指していきましょう。
東京都品川区YDC精密歯周病インプラント治療専門ガイド
監修:医療法人スマイルパートナーズ 理事長/齋藤和重
『山手歯科クリニック大井町』
住所:東京都品川区東大井5丁目25−1 カーサ大井町 1F
『山手歯科クリニック戸越公園』
住所:東京都品川区戸越5丁目10−18
*監修者
*経歴
1990年 鶴見大学歯学部卒業。1991年 インプラント専門医に勤務。1999年 山手歯科クリニック開業。
2001年 INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS卒業。
2010年 医療法人社団スマイルパートナーズ設立。
*所属
・ICOI国際インプラント学会 指導医
・ICOI国際インプラント学会 ローカルエリアディレクター
・ITI国際インプラント・歯科再生学会 公認 インプラントスペシャリスト
・日本口腔インプラント学会 会員
・日本顎顔面インプラント学会 会員
・国際審美学会 会員
・日本歯科審美学会 会員
・日本アンチエイジング歯科学会 会員
・INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS(2001年)
・CID Club (Center of Implant Dentistry)所属
・国際歯周内科研究会 所属
・5-D JAPAN 所属
・デンタルコンセプト21 所属
・インディアナ大学歯学部 客員 講師
・南カルフォルニア大学(USC)客員研究員
・南カルフォルニア大学(USC)アンバサダー
・USC (南カルフォルニア大学)歯学部JP卒
・USC University of Southern California)センチュリー・クラブ
・プレミアム・メンバー
※詳しいプロフィールはこちらより

